
なぜベストプラクティスを採用しても失敗してしまうのか
外部の手法に目を向けることで「自分たちの組織はどのように物事を進めているのか?」という内省的な問いが生まれ、組織の特性をより深く理解するきっかけになります。
デザインシステムの導入が組織内で広がらないなど課題に直面したとき、私たちはベストプラクティスを探すことがあります。たとえば、SalesforceのLightning Design SystemやIBMのCarbon Design Systemなど、大企業の事例は体系的に整理されており、私たち自身だけでなくステークホルダーにとっても理解しやすく、説得力があります。しかし、ベストプラクティスだからといって必ずしも成功するわけではなく、うまくいかないケースも少なくありません。
ベストプラクティスには不思議な魅力があります。道しるべとして頼りになる存在でありながら、うまくいかないことも多いです。一方で、手法や方法論を伝えたい立場も、できるだけ多くの人に役立つ方法を伝えたい気持ちと、「これは万能ではない」と伝えたい気持ちの間で揺れることがあります。
多くの人がベストプラクティスを求めていますが、なぜ期待した結果が得られないことがあるのでしょうか。
すれ違いが生み出す落とし穴
「ベストプラクティス」という言葉に関しては、過去に何度も議論されてきました。「これが成功率が高い手法です」という強いニュアンスを持つ言葉ですが、実際には文脈に依存した個人の信念に過ぎないという見解もあります。以下はアクセシビリティのベストプラクティスに関する記事ですが、デザインだけでなく、広い分野で共通する点があります。
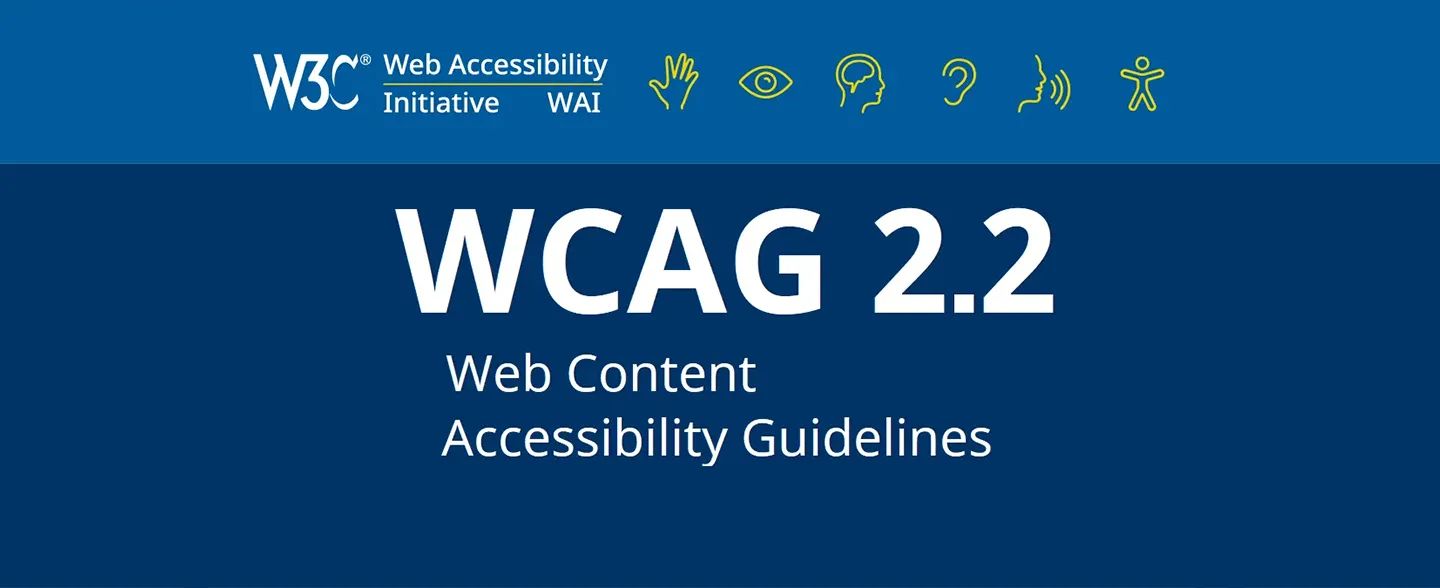
この問題の本質は「ベストプラクティス」という言葉の曖昧さだけではありません。実際、知識やノウハウを提供する側と求める側の期待に根本的なズレがあります。
知識やノウハウを提供する側は、経験したプロセスや直面した制約、試行錯誤の過程を含めて、文脈をしっかり共有したいと考えます。伝えるべきは具体的な手段や手順ではなく、「なぜそれが機能したのか」「どのような条件下で効果があるのか」といった背景情報です。一方で、ベストプラクティスをはじめとした情報を求める側は、時間的制約の中で、説明可能で再現性のある解決策を必要としています。上司や同僚に説明できる根拠、リスクを軽減できる先例を探しています。「どのような条件下で効果があるのか」といった知識は大切ですが、情報を求める人たちが求めているのは深い理解ではなく、目の前にある問題をいかに解決するかです。
他社の成功を根拠にすることで、言語化・共有が容易になります。組織での意思決定において「Aという会社がこの手法を使って成功した」という情報は、安全性を確保するための有効なでもあります。表面的に見えるかもしれませんが、実際に変化を推進するためには必要な場面があります。
一方で、間違いのない選択をしていると感じやすくなるバイアスも生まれやすくなります。このバイアスは「これを導入すれば上手く」といった、コピー&ペースト式の変革を引き出すことがあります。Spotify が生み出した「スクワッドの自主運営構造」は多くの組織が取り入れようとしましたが、同じ文化的背景や信頼ベースの文化が自社にないまま導入した結果、混乱、コミュニケーションギャップ、非効率につながったケースもあります。

ベストプラクティスとの良い付き合い方
これはベストプラクティスに価値がないという話ではありません。組織で新しい取り組みを始めるには相当なエネルギーが必要であり、ベストプラクティスは重要な推進力となります。実績のある手法として紹介できることで、ステークホルダーの理解を得やすくなり、予算や人的リソースの確保につながることも多いです。
問題は、ベストプラクティス自体ではなく、それとの向き合い方にあるのではないでしょうか。何かを始めるための『入口』として使えますが、組織の文脈に合う最適解ではないことが多いです。ただ、その前提を考慮してあえてベストプラクティスを試すことで、組織に合う手法の特徴が見えてくることがあります。
では、ベストプラクティスにどう向き合うべきでしょうか。ベストプラクティスを学ぶときや実践した後で、3つの視点(レンズ)で分析することで、組織に適した方法が見えてきます。
- 仕組みのレンズ : このベストプラクティスは、どのような技術制約、組織規模、開発プロセスを前提としているでしょうか。使用しているツールスタック、リソース配分、品質基準や評価指標はどのようなものだったのか。
- ビジネスのレンズ : どのような事業判断のもとで、そのアプローチが選択されたのでしょうか。リスク許容度、意思決定に求められるスピード、ステークホルダーの関心事や優先順位、予算制約やROIへの期待値。これらの要因が自分の状況とどう違うのでしょうか。
- チームのレンズ : ベストプラクティスが機能したチームは、どのような専門性レベルや経験値を持っていたでしょうか。コミュニケーションパターン、ユーザーとの距離感、フィードバックループの構造は自社とどう違うでしょうか。
うまくいかなかった時こそ、3つのレンズから観察することが重要です。これにより、「仕組みの前提が異なっていたために機能しなかった」や「リスクの許容は適切だったが、ステークホルダーの関心度に差があった」といった分析が可能になります。これが次の改善に具体性をもたらします。繰り返し分析することで、世にあるベストプラクティスが自社に合うかどうかもすぐに判断できるようになります。
ただ、こうした分析続けると、すべてのベストプラクティスが自社で使えないという結論に至ると思います。組織はそれぞれユニークなわけですから当然の結論です。「いいとこどり」のような部分的な適用も、かえって期待と異なる結果を招くことがあります。ベストプラクティスとして紹介されている手法は、一つの体系として全体が整合している からこそ成り立っています。部分的に切り出して適用しても、同じような効果は期待できません。
丸ごと移植もできず、部分的な適用も効果的でないとすれば、何が残るのでしょうか。
ベストプラクティスから抽出できる価値は、手法とは別のところにあるかもしれません。
- 思考の枠組みを理解する : なぜその判断をしたのか、何を重視していたのか、どのような制約の中で選択したのか。
- 注目すべき観点や問いかけ : 自分たちの文脈と重ねることで「この側面を見落としていたかもしれない」という気づきが得れることがあります。
- 問題を表現する言葉の発見 : 私たちがうまく言語化できていなかったことが、ベストプラクティスが適切な表現で提供されていることがあります。
- 失敗パターンにも注目 : 何がうまくいったかよりも、何がうまくいかなかったか、どこで軌道修正が必要だったかを理解する方が、異なる文脈でも応用しやすいことがあります。
自社の文脈の複雑さを理解していないままだと、ベストプラクティスで期待した結果が得られないことが多くあります。ベストプラクティスが生まれた環境と、それを適用しようとする環境の間には、表面的には見えない無数の違いがあります。組織文化、技術制約、ステークホルダーの関心事、チームの専門性など、様々な要因が相互作用し、同じ手法でも異なる結果をもたらします。
外部の手法に目を向けることで「自分たちの組織はどのように物事を進めているのか?」という内省的な問いが生まれ、組織の特性をより深く理解するきっかけになります。ベストプラクティスは万能薬ではありませんが、自分たちの文脈を見つめ直す役割を果たしてくれるはずです。


