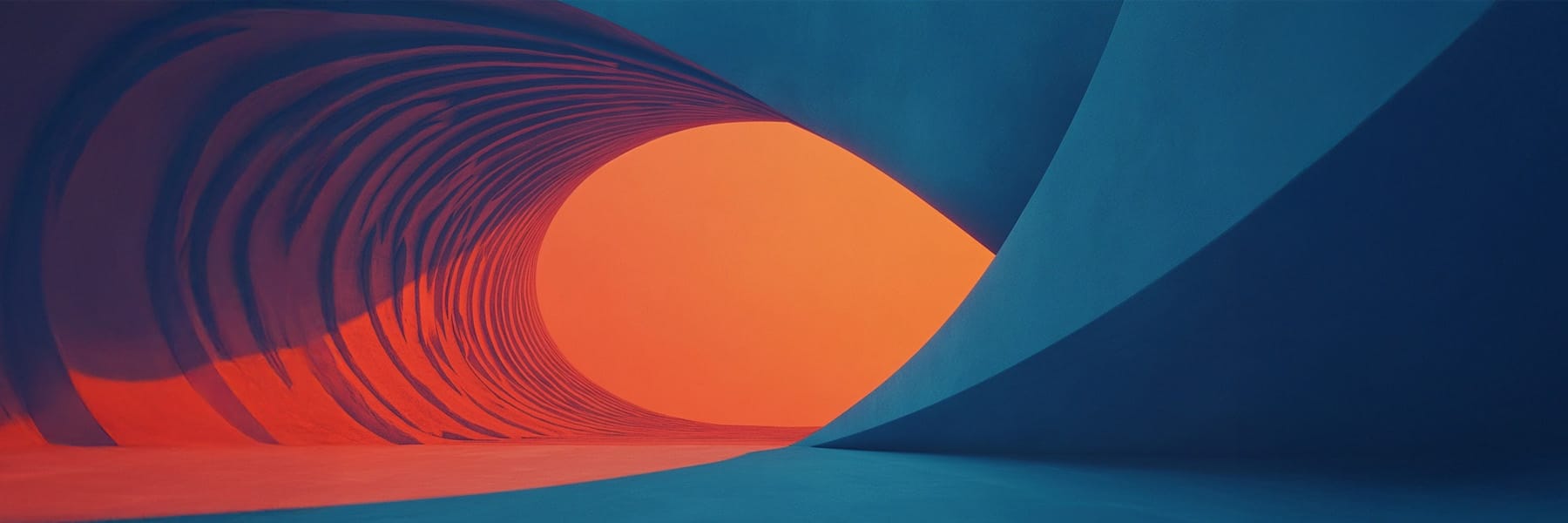
作ることから始まる新しい可能性
課題理解は重要ですが、それをプロセスの最初に行う必要があるのでしょうか。
プロトタイピングの民主化がもたらす変化
従来のデザインプロセスでは、まずユーザーリサーチで課題を特定し、プロトタイピングなどを通じて解決策を形にしていくのが一般的でした。私を含む多くのデザイナーは、課題を深く理解することがより良いアプリやWebサービスを作るうえで不可欠だと考えています。課題理解は確かに重要ですが、それをプロセスの最初に行う必要があるのでしょうか。最近、その点に疑問を感じ始めています。
利用規約を分かりやすく解説するミニアプリを、ClaudeのArtifact機能を使って作成しました。以前であれば、このようなアイデアを形にする際は、Figmaなどのデザインツールで画面遷移を示す「紙芝居」を作成していました。しかし今では、実際のデータを使って動作確認できる手段が増えています。この利用規約分析ツールも、わずか数分で実装することができました。
利用規約をこうやってザックリと理解するのもアリかもと思って作ってみた(💭判断軸をどこに置くかが難しいけど)。 pic.twitter.com/alD6WmulTn
— ヤスヒサ 🗑 (@yhassy) January 28, 2025
Claude 以外でも、Bolt や、v0 by Vercel のようなサービスを使って、とりあえずアイデアをかたちにできます。Web サイトであれば、WIXでプロンプトから生成を試すのもアリです(サーバーをたてるとか面倒なことを考えなくて済むのもメリット)。
プロセスを順序通り進めても、必ずしも良いアイデアが生まれるわけではありません。課題を理解し、コンセプトを練り上げることで優れたアイデアが生まれることはあります。しかし、とにかく多くのものを作ってみることで、偶然に良いアイデアに出会えることもあります。
グラフィックデザインの仕事をしていた時は、100個以上のアイデアを出すこともありました。一方、アプリのデザインでは、プログラミングの知識がないと試作を重ねることが難しく、デザインツールでできる範囲に制限されがちです。それが AI ツールによって「プログラミングの知識が必須」という制約から解き放たれることで、プロセスも変わるかもしれません。
今までのデザインの探索と検証は下記ようなステップがありました。
- ユーザーリサーチ
- 仮説構築
- プロトタイピング
- ユーザーテスト
- 修正・改善
従来のデザインプロセスで課題理解が最初に位置付けられていた背景には、プロトタイプ作成のコストが高かったという現実的な理由があったのかもしれません。確かに紙でスケッチするような簡易的な方法もありますし、プロトタイピングツールも進化を続けています。しかし、複数のアイデアを同時に検証したり、実際に動作する形で試作したりするには、相応の時間と労力が必要です。だからこそ、限られたリソースを有効活用するために、プロトタイプ作成の前に課題をしっかりと理解する必要があったのではないでしょうか。
もちろん、まったくの手がかりなしにいきなり作ることはできません。しかし、課題を深く理解する前にまず形にして、実際に目で見て触れることで新たな発見を得ることができます。作りながら、課題の輪郭が掴めることもあると思います。
変化を楽しみながら作り始めよう
プロトタイプ作成の敷居が下がれば、「ターゲットユーザーを設定してからでないと作れない」ではなく、「まだターゲットはぼんやりしているけど、とりあえず作ってみようか?」といった前向きな姿勢になりやすくなります。また、アイデアを1つや2つに絞る必要もなく、より自由な発想もしやすくなります。実機で動かせるものが作れるわけですから、アイデア作りも楽しくなります。
プロトタイピングのスピードが上がったからといって、リサーチが不要になるわけではありません。プロトタイプを多く作ることで「課題の輪郭を掴める」と述べたのも、それだけでは課題を深く理解することはできないからです。
合成データを活用したリサーチの可能性でも指摘したように、リサーチは今後さらに、人間の行動や心理の奥深い部分を探究する活動になっていくでしょう。プロトタイプを通じてさまざまな可能性を模索することで、新たな仮説や問いが生まれ、それをもとにリクルーティングやインタビューのシナリオを考えやすくなるかもしれません。
これまで以上にプロトタイプを活用した模索がしやすくなったとはいえ、注意すべき点もあります。「それっぽいもの」が早い段階で作れるのは利点ですが、そのまま勢いで進めてしまう恐れがあります。
「これが本当に解決すべき課題なのか」「そもそも私たちは課題を正しく理解しているのか」といった問いを立ち止まって考えることは不可欠です。こうしたコミュニケーションを意識しながら方針を固めることが、ブレないプロダクトを作るうえで重要になります。成果物の評価基準も同時につくっていかないと、なんとなく良い感じのアイデアを選ぶことになるので注意です。
AIによるプロトタイピングの進化は、デザインプロセスに大きな変化をもたらしています。これにより、課題発見のアプローチだけでなく、リサーチの役割自体も進化していくでしょう。
デザイナーの中には、課題の発見や理解から始めないプロセスに違和感を覚える人もいるかもしれません。しかし、実際に動くものを自分で作りながら模索できることは、大きな魅力でもあります。作ってみることで課題が明確になったり、新たなアイデアに出会う機会も増えるはずです。まずは、さまざまなサービスを試しながら「自分でも動作するものが作れるんだ!」という面白さを体験してみてください。
