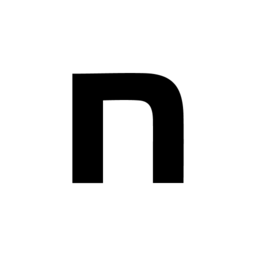なぜnoteでも記事を書き始めたのか
AIの進化により客観的な情報や実用的なノウハウが容易に手に入るようになった今、自分が書く意味は何か考えさせられます。
AIの進化によって、さまざまな情報を収集し、実用的なノウハウに落とし込むことが容易になりました。これまで専門家に聞くか、本や記事を読むしか得られなかった知識も、今ではAIとの対話を通じて簡単に手に入れられるようになっています。こうした状況の中で、自分は何を書き残せばよいのか、悩むことがあります。
もちろん、AIですべてを解決できるわけではありませんし、自分自身の記事もより深掘りしやすくなるため、チャンスだと捉えています。ただ、そうしたノウハウ的な情報提供に閉じこもることで、「自分が書く意味」が失われてしまうのではないかという懸念もあります。
では、生成AIでは難しい、人間らしい情報発信とは何でしょうか。そのひとつに「主観性」が挙げられます。
Haoran ChuとSixiao Liuによる2024年の研究では、AIが生成した物語には行動に影響を与える可能性があるものの、深く持続的な人間関係を築くために必要な繊細さや感情的な複雑さが欠けていることが示されています。つまり、AIは個人的な経験や人間感情への深い理解を持たないため、生成される物語も、特に感情的な共感や深い人間関係を描く場面では限界があります。

📎 Can AI tell good stories? Narrative transportation and persuasion with ChatGPT
AIは「正しい情報」や「役立つノウハウ」を生成することはできても、主観的な見解や体験を生み出すことはできません(少なくとも現時点では)。データや事例だけでは伝わらない独自の視点や解釈を提供することが、作り手と受け手の間に新たな関係性を築くきっかけとなるかもしれません。もちろん、そこには誤りや偏りが含まれる可能性もありますが、あえて共有することで、互いに貴重な視点を得る機会にもなるはずです。
そうした自分の感じたことや考えていることを書き出すために、先月からnoteを始めました。役に立つ実践的な情報ではなく、私が感じたことを短くまとめています(すべて30秒以内で読めます)。

こちらは参照するリンクも事例もない、主観に振り切った記事ばかりです。
正しくないかもしれないし、定説から外れているかもしれません。それでも、自分自身の視点で語られた体験は、他者の心に残り、新たな対話を生み出す力を持っていると思います。AIと共存する時代においては、自分にしか書けないことを言葉にし、自分なりの解釈を絵にして表現することが、貴重な可能性を生み出すのではないでしょうか。
記事をnoteへ引っ越しするのではなく、しばらく併用しながら使い分けていく予定です。これからもこのサイトでは、複雑な状況下で働くデザイナーにとってヒントになりそうな実践記事を配信していきます(すでに下書きの記事もいくつかあり、長めの記事も準備中です)。答えのないもやもやした感覚をのぞいてみたい方は、ぜひnoteも読んでみてください😀